マイバイク紹介
Crin blanc
- 年齢:30代
- 体重:56-60
- 身長:171-180
- スポーツバイク暦:14年
- 属性:ポタリング志向
- 脚質:クライマー
- 総走行距離:129.2 km
- このバイクの走行距離:129.2 km
| 購入時期 | 比較検討したバイク |
|---|---|
| 2016/06 | ー |
| 購入の決め手 | |
|
もともとフランス製の古いロードバイクに乗っており、ひょんなことから手放してしまいました。そしてしばらく歳月を経てまたロードバイクに乗りたいと思い、探したところ、今のロードバイクに出会いました。 レトロかつきちっと作り込まれたデザインで一目惚れしました。 やはり古くてもしっかり作られたものは世代を超えますね。 愛車の名前は1953年公開のフランス映画Crin blancから。 ちなみに和名では白い馬です。 プライドの高い生粋のフランス人である愛車にフランス語以外の名前をつけると怒り出しそうなので。笑 |
|
スペック
-
- フレーム
-
Peugeot PA10
-
- ホイール
-
Super Champion
-
- サドル
-
Ideal France 51 Cyclocross
-
- タイヤ
-
- コンポーネント
-
Simplex Prestige
-
- ペダル
-
Maillard
-
- ハンドル
-
Phillips
-
- ステム
-
AVA
-
- その他
-
mafac dual hodges kool stop brake pads "Dry" Christophe half clip シェラックニス仕上げハンドルバー Simplex Chainring 46T-50T Nervar Crankset 170mm Maillard atomスプロケット14T-28T maillard normandy maillard atom freewheel
みんなの感想
かっこいい!
 (1)
(1)
マニアック!
 (2)
(2)
リスペクト!
 (3)
(3)
参考になった!
 (1)
(1)























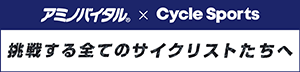




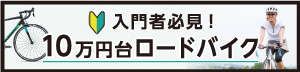




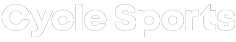
オーナーのコメント
デカールとフレームに刻印されたシリアルナンバーを元に当時のカタログやインターネットから情報を調べたところ、このバイクは1963年Peugeot製PA10であることが判明。
ただ、当時のスペックを調べていくのは少しばかり大変でしたが基本的なことは把握することができました。
まずフレームはハイテン鋼製のチューブをNervex製のProfessionalとSERIE Legereを組み合わせたラグ溶接。
当時のカタログでは総車体重量11kgと記載されていました。
上位機種であるPX10と同じフレームジオメトリを用いられたものです。
しかしPX10は9.5kg、Reynolds 531ダブルバテットチューブ、オールマンガンモリブデン製とやはりグレードの差はあります。
兄弟車であるPY10は前三角がマンガンモリブデン、その他パーツはハイテン鋼という仕様で僕の所持するPA10はその中でも末っ子的な存在だったのでしょう。
値段に関しても当時のPX10の半分くらいだったようです。出会ったバイクとは末長く付き合っていきたいという一心で一通りのレストアをしました。
やはりフレームがフランス規格であることからネジのパターンやパーツの汎用性など癖のある箇所が多くそれなりに情報を調べて作業を進めていきました。
レストアの内容ですが各部回転部の清掃、ベアリング交換、グリスアップはもとより表面に付着していた錆を落としたり、また磨いたり。
購入時の状態からは見違えるような走行性能を取り戻すことができました。
フレームの塗装はあえて今までこのバイクが歩んできた歴史を物語るところなので必要最低限のサビ落としのみにしました。
きちっと作られたものは何年たっても整備はある程度やり易いと思います。
フレーム精度がしっかりと出ていたのには感心しました。
もともとついていたCYCLO製リアスプロケットが5Sで14T-19T、フロントチェーンリングが46T、50Tとギア比を計算すると大変な男ギアでした。
インナーローにて2.42では街中にある坂を登る時も一苦労。
そこで純正のSuper Champion製RecoadチューブラーリムをRIGIDA製の鉄リムに交換した際についていたMaillard製スプロケット14T-28Tの少しワイドなものに交換しました。
インナーローにて1.64のギア比で使用でき、15%くらいの激坂が続く峠でもダンシング、シッティングと組み合わせてなんとか登れるようになりました。
前輪はSuper Championのアルミリム、後輪にRIGIDAの鉄リムを装着し、タイヤはスレックタイヤでは安くてそれなりなMichelin Dynamic Sport 23mmを履いてます。
平地では漕ぎ出しが少し重いものも、スピードにある程度乗ってしまえは楽にスピードを維持できます。
街中での僕の巡行スピードはケイデンス90rpmくらいで25-30kmくらいでしょうか。
道がひらけた平地では40kmちょいを出すこともできます。
今後は今ついているSimplex製のチェーンリング46T-50Tをもう少しコンパクトなコッターレスのStronglight製の41T-52Tに変更し、もともとついていたCYCLO製リアスプロケットに戻し、クロスレシオで走行したいです。
もし見つけられたらクランク長も175mmのものに変更したいなと考えています。
昔のロードバイクは今のSTIレバーのブラケットを握って走行するスタイルではなく下ハンを握って走行するということもあったせいか、シートピラーが短めに作られており、そこまで高くは調整できません。
現在はシートチューブの中に3cmもピラーが入っていない状態です。
それに僕のようにブレーキブラケットの手前を握るポジションでサドルの高さを合わせてしまうとなんとなくハンドル落差がつき過ぎてしまい、前傾姿勢がとても強くなってしまいます。
ステムをあげると今度はトップチューブが短くなりすぎてしまうし、まだまだ最適なポジション出しには苦労しそうです。ピラーだけでももう少し長いものに変更したいのですがアルミ製の24mmのものがなかなか見つかりません。
ポッキリと折れないように祈るばかりです。
しかし整備を繰り返してその効果を直に体感できるのでとても楽しいです。
老体に鞭を打ってまだまだ乗り続けたいと思います。